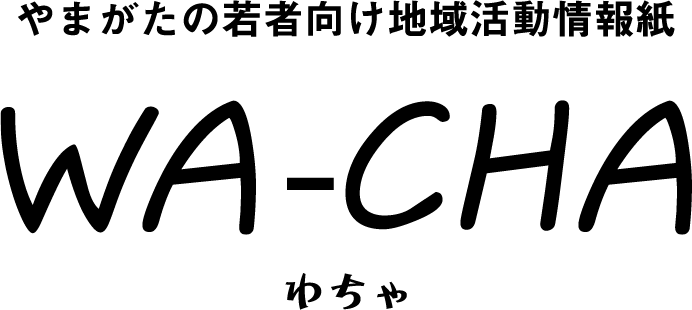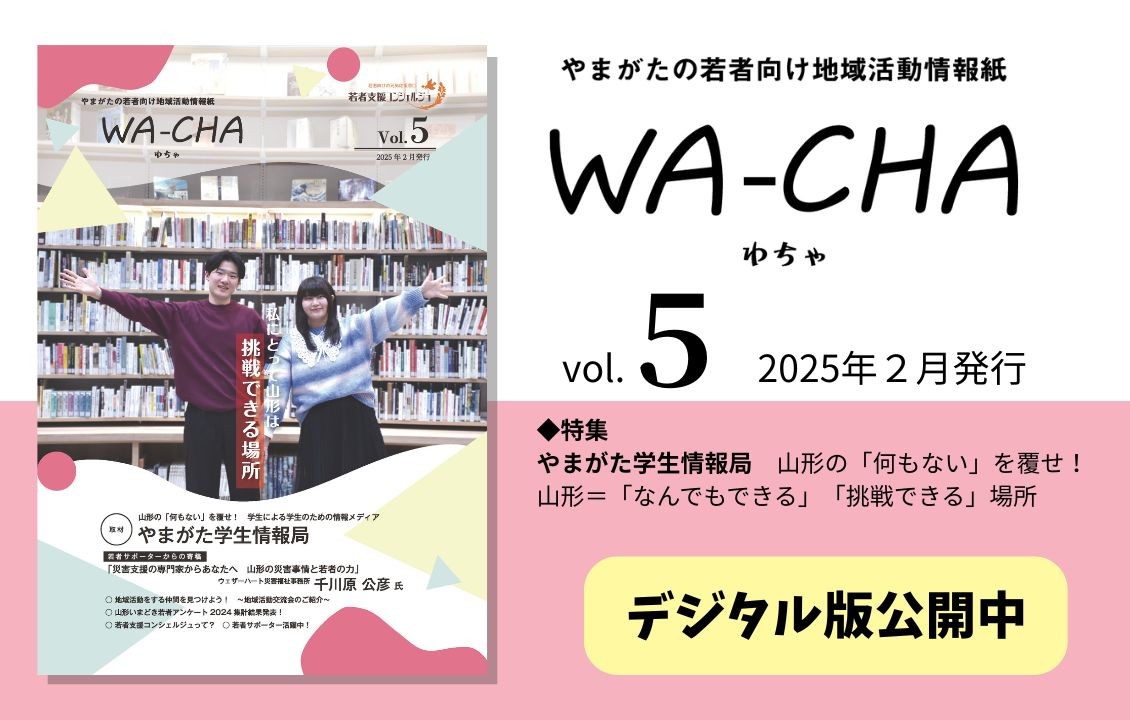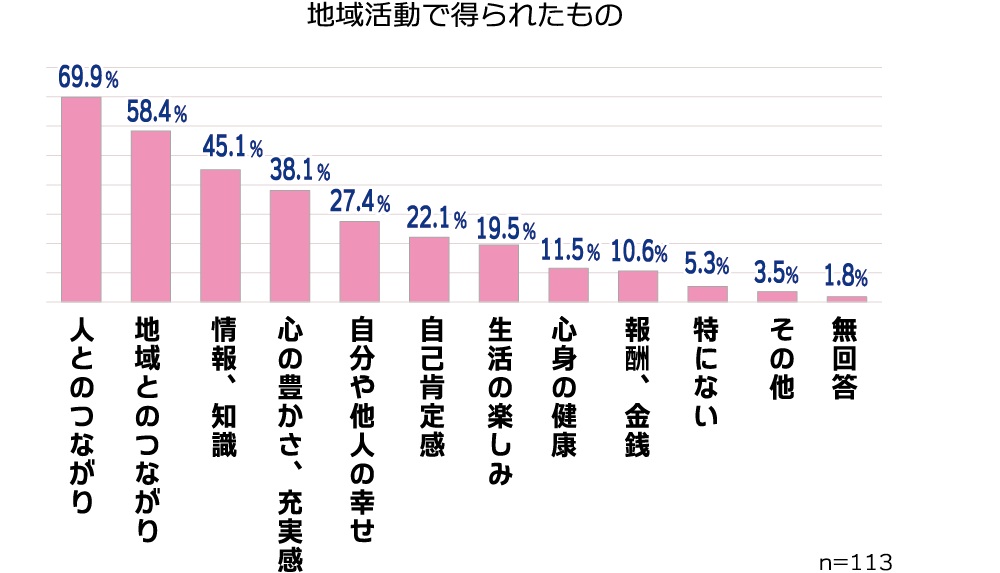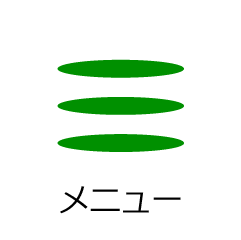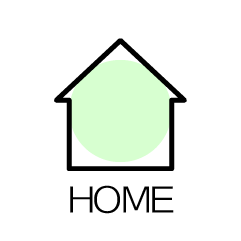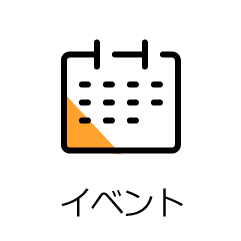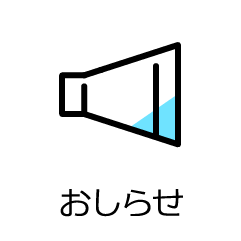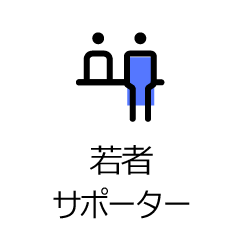ウェザーハート災害福祉事務所 代表
ウェザーハート災害福祉事務所 代表
若者サポーター
山形県出身。秋田県在住時に、「日本海中部地震(1983,秋田県)」を体験。 「有珠山噴火災害 (2000,北海道)」を契機に、全国での災害支援活動に関わる。 平時は、行政・社協・自治会・NPO等とともに防災訓練・災害研修等の企画など、社会福祉協議会・NPO・住民等と関わりながら、協働を重視した活動を心がけている。
「能登半島地震クラス」の大地震が起きるかもしれない山形県
2024年の元日に発生した能登半島地震では、400名以上の命が失われました。
半数は地震や津波によるもの、そして半数はその後の過酷な避難生活中に亡くなった災害関連死でした。
山形は災害が少ないと言われていますが、実際はどうなのでしょうか?
山形にも大地震の原因になる活断層が複数あります。国の方では山形の活断層を「危険度の高いSランク」に指定しており、犠牲者は最大で約2千人、避難者も20万人となる大地震になるだろうと言われています。実は、能登半島地震クラスの大地震がいつ起きてもおかしくないのが山形県の現状です。

自分の命を守る意識
加えて、2年に一度の頻度で、山形では洪水・土砂災害が発生しています。
いつ災害が起きても不思議ではない山形県ですから、「自分の命を守る意識」を高めることが大切です。
阪神・淡路大震災(1995年)では、犠牲となった0~40歳未満の内、一番多く亡くなったのは20代の若者でした。一人暮らしが多かったり、出費を抑えるために耐震の弱い建物で生活していた学生が多かったりしたこと等が原因だと言われています。
災害が起きる前に、地震に備えて「家具を固定」したり、洪水・土砂災害から命を守るために「ハザードマップで避難所を確認」したりすることが大切です。

災害時に必要とされている「若者の力」
そして、大きな災害が起きると、地域には「避難所」や「災害ボランティアセンター」が開設されます。
自宅で発生したガレキや汚泥の処理は、基本的に自力で行う「自己責任、自己完結」になっていますが、高齢者や障がい者の世帯でそれを行うことは無理に等しいものがあります。山形は高齢者も多く、県民の約35%が65歳以上です。
そこで必要になってくるのが「若者の力」です。
一方で、国が公表した情報(12年、21年)では、ボランティアの年齢層を見ると、全国的に40代以上の参加が多く(年代毎にそれぞれ20%程度)、10~20代についてはそれぞれ15%に留まっており、まだまだ伸び代がある状況です。
避難所や災害ボランティアセンターでは人材不足に困っているケースが多いので、災害時、時間的な余裕があればボランティアとして参加してみてはいかがでしょうか?
そのためには、災害で「死なない、ケガをしない」ことが大切です。若者の防災意識が高まることで、次のフェーズである「助け合い」、ひいては「一日も早い山形の復旧・復興」に繋がるものと思います。
千川原さんのお話をもっと聞きたいときは若者サポーターを利用できます
若者サポーターでは、さまざまな分野のスペシャリストや実践者に、お話を聞くことができます。
疑問や悩みが解決するヒントが見つかるかも? お気軽にご相談ください!